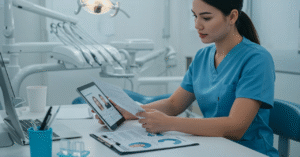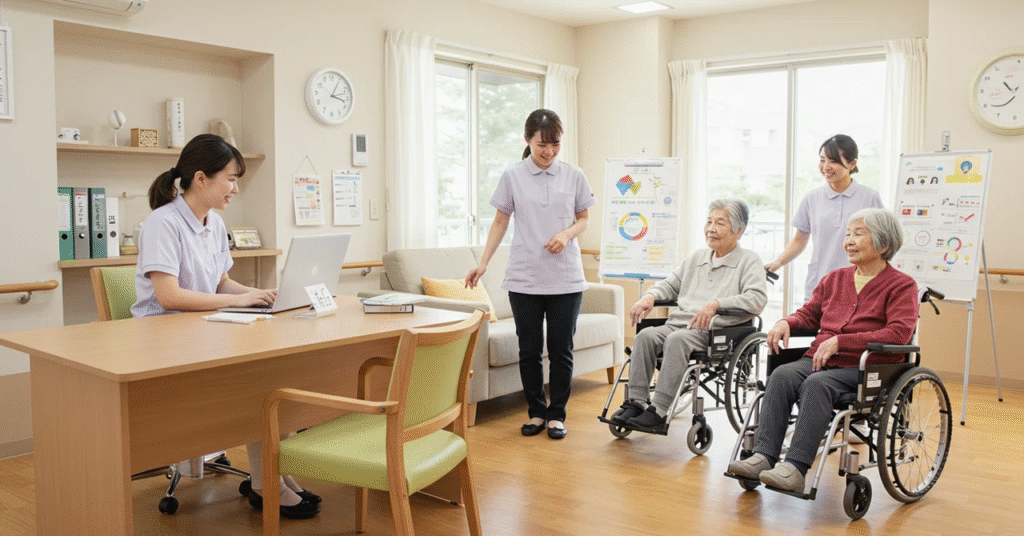
介護職の採用課題と応募者の質の重要性
介護業界では人材不足が深刻化する中、単に「人数を確保する」だけでは、もはや組織の持続的な成長は望めません。質の高い人材を採用することが、サービスの質向上と職場環境の安定に直結するようになっています。
現場の声を聞くと、「応募はあるけれど、すぐに辞めてしまう」「期待していた能力や意欲が見られない」という悩みが絶えません。
では、なぜ介護職の応募者の質にこだわる必要があるのでしょうか?
質の高い介護職員が組織にもたらす価値は計り知れません。利用者のQOL(生活の質)向上に直接貢献するだけでなく、職場の雰囲気を良くし、他のスタッフの定着率向上にも影響するからです。

「いい人材が来ない」と嘆く前に、まずは自分たちの採用アプローチを見直してみませんか?
本記事では、中小介護事業者が実践できる「応募者の質を向上させる8つの効果的なアプローチ」を紹介します。2025年の最新動向を踏まえた実践的な方法ばかりですので、ぜひ最後までお読みください。
1. 求人情報のリフレーミングで応募者の質を高める
多くの介護事業者が「人が集まらない」と悩む中、実は求人情報の「見せ方」を変えるだけで応募者の質が大きく変わることをご存知でしょうか?
この手法は心理学用語で「リフレーミング」と呼ばれ、物事の枠組みを変えて違う視点から見せることを意味します。介護業界でも、この考え方を取り入れた求人が成果を上げ始めています。
ネガティブな印象を払拭する表現の工夫
介護職は依然として「3K(きつい・汚い・危険)」というネガティブなイメージが付きまとっています。しかし、求人情報の表現を工夫するだけで、応募者の心理的ハードルを下げることができるのです。
例えば、「介護助手」という職名は、「助手」という言葉から「上下関係が面倒そう」という印象を与えかねません。これを「生活サポートスタッフ」や「シニアライフサポーター」といった前向きな印象の職名に変えるだけで、応募者の質と量が向上した事例があります。

岡山県瀬戸内市での実験では、「介護助手」という名称を「洗濯・掃除・食事の配膳等の補助スタッフ」と具体的に変更しただけで、応募者の質が向上したという結果が出ています。
具体的な業務内容の明示
「介護職員」という曖昧な表現では、応募者は「どんな仕事をするのか」イメージできません。「介護福祉士」「ケアマネジャー」など、具体的な職種名を使い、業務内容を明確に伝えることで、ミスマッチを減らすことができます。
職種名をより具体的にすればするほど、そのターゲットからの応募が来る可能性が高まります。これは単なる言葉遊びではなく、応募者の心理的不安を取り除く重要なアプローチなのです。
2. 中小事業者ならではの強みを活かした採用戦略
大手介護施設との人材獲得競争で勝つには、中小事業者ならではの強みを最大限に活かすことが重要です。実は、規模が小さいことが逆に大きな武器になるんです。
私が以前、ある小規模デイサービスの採用支援をした時のこと。「大手には敵わない」と諦めかけていた施設長が、自分たちの強みを見つけ、発信し始めたところ、わずか3ヶ月で5名の質の高い介護職員を採用できました。
アットホームな職場環境をアピール
中小介護事業者の最大の強みは「アットホームな職場環境」です。大手では実現できない「家族的な雰囲気」や「意見が通りやすい風通しの良さ」は、多くの求職者、特に人間関係を重視する介護職志望者にとって大きな魅力となります。

実際に、明石市が発行している「あかしの福祉の好事例集」では、アットホームな環境づくりに成功している施設の事例が多数紹介されています。そこでは、スタッフ同士の距離が近く、意見交換がしやすい環境が離職率低下につながっていることが報告されています。
成長機会の提供と明確なキャリアパス
中小事業者だからこそ提供できる「一人ひとりに合わせた成長機会」も大きな強みです。大手では難しい「個別のキャリアプラン」や「多様な業務経験」を提供できることをアピールしましょう。
静岡県の優良介護事業所表彰を受けた施設では、職員一人ひとりの強みを活かした役割分担と、明確なキャリアパスの提示が、質の高い人材確保につながっていると報告されています。
あなたの施設でも、「ここでどう成長できるか」を具体的に示すことで、将来を見据えた質の高い応募者を惹きつけることができるでしょう。
3. 採用基準の明確化と選考プロセスの最適化
質の高い応募者を見極めるには、明確な採用基準と効率的な選考プロセスが欠かせません。実は、多くの介護事業者が「人手不足だから誰でも採用してしまう」という罠に陥っています。
しかし、そのような場当たり的な採用は、長期的に見れば離職率の上昇や職場環境の悪化を招き、さらなる人材不足という悪循環を生み出すのです。
理念に基づいた採用基準の設定
まず必要なのは、自施設の理念や価値観に基づいた明確な採用基準です。「どんな人材が自分たちの施設に合うのか」を具体的に言語化しましょう。
技術や資格だけでなく、「チームワークを重視する姿勢」「利用者に対する共感力」「成長意欲」など、数値化しにくい要素こそ、長く活躍できる人材を見極めるポイントになります。
静岡県の優良介護事業所表彰を受けた施設では、「利用者一人一人の個性や生活リズムを尊重する姿勢」を重視した採用基準を設け、それに基づいた独自の面接手法を開発しています。
効果的な選考プロセスの構築
次に、その基準を適切に評価できる選考プロセスを構築します。一般的な「書類選考→面接」だけでなく、「現場見学」「模擬ケアの実施」「チームメンバーとの交流」など、多角的に候補者を評価する機会を設けましょう。

ある関西地方の特別養護老人ホームでは、応募者に実際の業務を体験してもらう「職場体験型選考」を導入したところ、採用後のミスマッチが大幅に減少し、採用業務時間も50%削減できたそうです。
採用担当者だけでなく、現場スタッフも選考に関わることで、「チームに馴染めるか」という視点も評価できます。
あなたは応募者を選ぶ立場ですが、優秀な人材は「職場を選ぶ」立場でもあることを忘れないでください。選考プロセス自体が、あなたの施設の価値観や文化を伝える重要な機会なのです。
4. 応募者の質を高めるための情報発信戦略
質の高い応募者を惹きつけるには、求人情報だけでなく、日頃からの情報発信が重要です。実は、応募を検討する前に、多くの求職者があなたの施設について「こっそり調査」しているのをご存知ですか?
「この施設で働いたらどんな毎日が待っているんだろう?」
そんな疑問を抱いた求職者は、あなたの施設のウェブサイトやSNSをチェックします。そこで魅力的な情報が見つからなければ、応募には至りません。
リアルな職場の日常を伝える
施設の理念や概要だけでなく、「実際にそこで働く人々の日常」を伝えることが重要です。スタッフの声、日々の業務風景、チームの雰囲気など、リアルな情報が求職者の不安を取り除きます。
九州地方のあるグループホームでは、スタッフが交代で日々の業務や感じたことをブログに投稿する取り組みを始めたところ、「この施設で働きたい」という質の高い応募が増え、2ヶ月で2名の採用に成功しました。
利用者のQOL向上への取り組みを発信
介護職を志す人の多くは「人の役に立ちたい」という思いを持っています。あなたの施設が利用者のQOL(生活の質)向上にどう取り組んでいるかを発信することで、同じ価値観を持つ質の高い応募者を惹きつけることができます。

「令和6年版高齢社会白書」によると、社会活動に参加している高齢者の84.4%が生きがいを感じていると報告されています。このようなデータを活用しながら、あなたの施設での具体的な取り組み事例を発信することで、専門性の高さをアピールできます。
職員の成長ストーリーの共有
「この施設で働くとどう成長できるのか」を具体的に示すことも効果的です。現職員の成長ストーリーや、研修制度、キャリアパスなどを発信しましょう。
静岡県の優良介護事業所表彰を受けた施設では、職員の成長事例を定期的に発信することで、「ここで働けば成長できる」というイメージを定着させ、意欲の高い応募者の獲得に成功しています。
情報発信は一朝一夕にはいきません。しかし、継続的な発信が、やがてあなたの施設の「ブランド」を形成し、質の高い応募者を自然と惹きつける磁石となるのです。
5. 介護職の働きがいと価値の再定義
介護職の応募者の質を高めるには、介護という仕事の「働きがい」と「社会的価値」を再定義し、明確に伝えることが重要です。なぜなら、多くの質の高い人材は「給料だけ」で職場を選ぶわけではないからです。
私は10年以上介護業界に携わってきましたが、長く活躍している介護職員に共通するのは「この仕事の意義を見出している」ということ。その「意義」をどう伝えるかが、質の高い応募者を惹きつける鍵になります。
介護職の社会的意義の明確化
超高齢社会の日本において、介護職は単なる「お世話をする仕事」ではなく、「人生の最終章を支える尊厳ある仕事」です。この社会的意義を明確に伝えることで、「社会貢献したい」という思いを持つ質の高い人材を惹きつけることができます。
厚生労働省の「介護サービスにおける生産性向上のとらえ方」でも、介護の価値を「一人でも多くの利用者に質の高いケアを届ける」と定義しています。このような大きな視点から介護の価値を伝えることが重要です。
個人の成長につながる仕事であることの強調
介護職は「人間力」が鍛えられる仕事でもあります。コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワーク、忍耐力など、人生のあらゆる場面で役立つスキルが身につきます。
関東地方のあるデイサービスでは、「介護で学ぶ7つの人間力」という独自のフレームワークを作り、採用活動に活用したところ、異業種からの質の高い転職者が増えたそうです。
やりがいを感じる瞬間の共有
「利用者さんの笑顔を見た時」「小さな成長に立ち会えた時」「感謝の言葉をもらった時」など、介護職ならではの「やりがいを感じる瞬間」を具体的に伝えることも効果的です。
抽象的な「やりがいがあります」という言葉ではなく、現場スタッフの実際のエピソードを交えて伝えることで、リアリティのある「働きがい」を伝えることができます。
介護職の価値を再定義し、その魅力を伝えることは、単に「人を集める」だけでなく、「志を同じくする仲間を集める」ことにつながります。それが結果的に、組織全体の質の向上をもたらすのです。
6. テクノロジー活用による業務効率化と採用力強化
介護業界でもデジタル化が急速に進む2025年。最新テクノロジーを活用することで、業務効率化と採用力強化の両方を実現できます。実は、テクノロジー活用は「人を大切にする」ことと矛盾しないんです。むしろ、その逆なんですよ。
私が支援したある特別養護老人ホームでは、記録システムの導入により、スタッフの残業時間が月平均15時間から5時間に減少。その結果、「ワークライフバランスを重視できる職場」として評判が広がり、質の高い応募者が増えました。
業務効率化で「人にしかできない仕事」に集中
介護記録の電子化、見守りセンサーの導入、コミュニケーションツールの活用など、テクノロジーで効率化できる業務は多くあります。これにより、スタッフは書類作成などの間接業務から解放され、「人にしかできない質の高いケア」に集中できるようになります。
厚生労働省の「介護サービスにおける生産性向上のとらえ方」でも、業務改善の視点から取り組む生産性向上の取組が推奨されています。テクノロジー活用はその中心的な施策の一つです。
先進的な職場環境のアピール
最新テクノロジーを積極的に導入している施設は、「先進的で働きやすい職場」というイメージを求職者に与えます。特に若い世代の応募者にとって、デジタル化された職場環境は大きな魅力となります。
介護付きホーム研究サミット2025の事例では、「AIやテクノロジーを活用した介護サービスの質の向上」に取り組む施設が、若手人材の獲得に成功していることが報告されています。
採用プロセス自体のデジタル化
採用活動自体にもテクノロジーを活用しましょう。オンライン面接、デジタル職場見学、採用管理システムの導入など、応募者の利便性を高めることで、質の高い人材を惹きつけることができます。
特に地方の介護施設では、遠方からの応募者とのオンライン面接を導入することで、採用範囲を大幅に広げることができます。
テクノロジー活用は「人間味のある介護」と対立するものではありません。むしろ、テクノロジーによって効率化された時間を、より質の高い人間的なケアに充てることができるのです。そのビジョンを明確に伝えることで、未来志向の質の高い人材を惹きつけることができるでしょう。
7. 既存スタッフの満足度向上による採用力強化
質の高い応募者を惹きつける最強の武器は、実は「現在働いているスタッフの満足度」なのです。なぜなら、職場の本当の姿は、そこで働く人々の表情や言葉に最も正直に表れるからです。
「うちの職場、最高だよ!」
そう心から言えるスタッフがいる職場には、自然と質の高い人材が集まってきます。逆に、現場スタッフの不満が高い職場では、いくら採用活動に力を入れても、本当に欲しい人材は逃げていってしまうでしょう。
働きやすい職場環境の整備
静岡県の優良介護事業所表彰制度では、「離職防止・定着促進」「人材育成」「働きやすい職場づくり」に取り組む施設が表彰されています。これらの取り組みは、既存スタッフの満足度を高めるだけでなく、「ここで働きたい」と思わせる施設の魅力にもなります。
具体的には、柔軟なシフト制度、休暇取得の促進、心身の健康サポート、コミュニケーション活性化など、スタッフが「長く働きたい」と思える環境づくりが重要です。
スタッフの成長を支援する文化
「この職場で成長できる」と実感できることも、スタッフの満足度を高める重要な要素です。研修制度の充実、資格取得支援、キャリアパスの明確化など、一人ひとりの成長を支援する文化を作りましょう。
明石市の「あかしの福祉の好事例集」では、職員教育の工夫に取り組む施設の事例が多数紹介されています。そこでは、個々のスタッフの強みを活かした育成プランが、職場の活性化と採用力強化につながっていることが報告されています。
「口コミ採用」の促進
満足度の高いスタッフは、自然と周囲に「うちの職場はいいよ」と伝えます。この「口コミ採用」は、採用コストが低く、かつミスマッチも少ない最も効率的な採用方法です。
「社員紹介制度」を設け、既存スタッフからの紹介を積極的に奨励することも効果的です。紹介者へのインセンティブを用意することで、より質の高い人材の紹介につながります。
既存スタッフの満足度向上は、離職率低下と採用力強化の両方に効果があります。「採用」と「定着」は別々の問題ではなく、同じコインの裏表なのです。スタッフが生き生きと働ける職場づくりこそ、質の高い応募者を惹きつける最大の秘訣なのです。
8. 専門的な採用支援サービスの活用
中小介護事業者にとって、採用活動に十分なリソースを割くことは容易ではありません。「採用したいけど、時間も専門知識も足りない…」という悩みを抱える経営者や管理者は少なくないでしょう。
そんな時、専門的な採用支援サービスの活用が効果的な解決策となります。
中小介護事業者専門の採用支援サービス
近年、中小介護事業者に特化した採用支援サービスが増えています。これらのサービスは、大手とは異なる中小事業者の特性や魅力を理解し、それを最大限に活かした採用戦略を提案してくれます。
例えば「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用課題解決サービスでは、月額定額制で採用業務を完全代行し、初期費用無料、成果報酬無料、求人掲載費込みの明確な料金体系を提供しています。
戦略的求人設計のプロフェッショナル活用
採用のプロフェッショナルは、「どうすれば応募者の質を高められるか」を熟知しています。大手施設との差別化を図る独自の求人戦略の策定、魅力的な求人原稿の作成、最適な求人媒体の選定など、専門的なノウハウを活用できます。
関東地方のあるデイサービスでは、採用支援サービスを活用して求人戦略を見直したところ、3ヶ月で5名の質の高い介護職員の採用に成功しました。
積極的スカウト活動の実施
「待ちの採用」から「攻めの採用」へ。専門スタッフが求職者一人ひとりに丁寧にアプローチし、施設の魅力を直接伝えることで、優秀な人材を獲得できます。
特に、現在は転職を考えていないけれど、条件が合えば動く可能性のある「潜在的求職者」へのアプローチは、専門家のネットワークがあってこそ可能になります。
業界ネットワークの活用
優良な人材紹介会社とのパートナーシップも、質の高い人材確保の重要な鍵です。中小事業者の価値を理解した紹介会社から、質の高い人材を継続的に紹介してもらうことができます。
採用支援サービスを活用することで、採用業務の負担を軽減しながら、より戦略的で効果的な採用活動を展開することができます。「人材は最大の経営資源」と言われる時代、この投資は必ず将来の組織の成長につながるでしょう。
まとめ:質の高い介護人材確保への道筋
介護職応募者の質を向上させる8つのアプローチを紹介してきました。これらは単独でも効果がありますが、組み合わせることでさらに大きな成果を生み出します。
最後に、これらのアプローチを実践する上で重要なポイントを3つお伝えします。
まず、「量」より「質」を優先する勇気を持つこと。短期的には人手不足感があっても、質の高い人材を厳選することが、長期的な組織の安定と成長につながります。
次に、採用活動は「一方通行」ではなく「相互選択」であることを忘れないこと。質の高い人材は職場を選ぶ立場でもあります。あなたの施設が「選ばれる職場」になるための努力を惜しまないでください。
そして最後に、採用は「点」ではなく「線」で考えること。一時的なキャンペーンではなく、日々の情報発信や職場環境の整備など、継続的な取り組みが質の高い応募者を惹きつける磁石となります。
介護人材の確保は、今後も介護業界の最重要課題であり続けるでしょう。しかし、「人が集まらない」と嘆く前に、まずは自分たちの採用アプローチを見直してみてください。
質の高い介護人材の確保は、利用者のQOL向上、職場環境の改善、そして事業の持続的成長につながる重要な投資です。本記事が、あなたの施設の採用力強化の一助となれば幸いです。
介護職の採用でお悩みなら、中小介護事業者専門の採用課題解決サービス「かいごのおたすけ採用隊」にご相談ください。月額10万円で採用業務を完全代行し、質の高い介護人材の確保をサポートします。詳細はこちらからご確認いただけます。