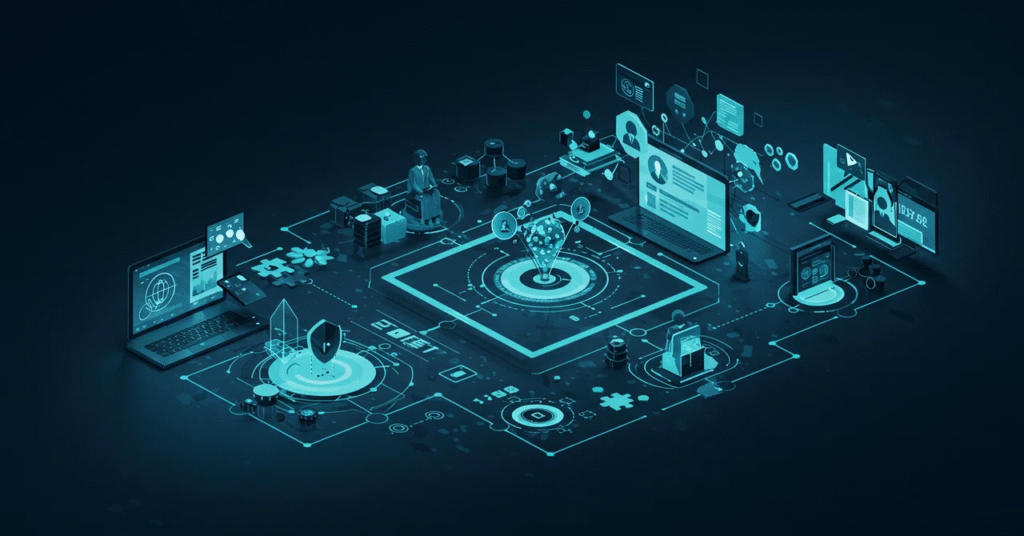
2025年採用市場の現状と課題
「採用したくても人が集まらない」
これは今、多くの企業が直面している深刻な課題です。2025年の採用市場は、少子高齢化の加速と労働人口の減少により、かつてないほどの売り手市場となっています。帝国データバンクの最新調査によれば、人手不足を感じている企業の割合は51.7%と高水準が続いており、コロナ禍で一時的に緩和したものの、経済回復とともに再び深刻化しています。
特に2025年は「2025年問題」と呼ばれる社会的課題が顕在化する年でもあります。内閣府の発表によると、65歳から74歳の前期高齢者が1,497万人、75歳以上の後期高齢者が2,180万人に達し、64歳以下の労働者層が減少する見込みです。

この状況下で企業の採用担当者は頭を抱えています。採用コストは上昇し、理想の人材との出会いは困難になり、若手へのアプローチ不足や採用活動の長期化など、多くの課題が山積しています。
あなたの会社でも似たような悩みを抱えていませんか?
本記事では、2025年の採用市場の最新トレンドと、それに成功裏に対応している企業の事例を徹底解説します。今後の採用戦略を立てる上での具体的なヒントが必ず見つかるはずです。
2025年採用市場の5大トレンド
採用市場は常に変化していますが、2025年は特に大きな転換点を迎えています。最新のデータと市場調査から、今押さえておくべき5つの重要トレンドが浮かび上がってきました。
これらのトレンドを理解し、自社の採用戦略に取り入れることが、厳しい人材獲得競争で優位に立つための鍵となるでしょう。マイナビキャリアリサーチLabの最新調査によれば、2025年7月時点の中途採用実施率は39.4%、今後3ヶ月以内の中途採用予定率は60.5%と、企業の採用意欲は依然として高い水準を維持しています。
1. リモートワーク対応の強化
コロナ禍をきっかけに広がったリモートワークは、今や一時的な対応策ではなく、働き方の新たなスタンダードとなりました。2025年の採用市場では、リモートワークに適した人材の確保が重要課題となっています。
自己管理能力が高く、オンラインでのコミュニケーションスキルに長けた人材が特に求められています。採用面接においても、時間管理能力やITツールの活用スキルを重視する企業が増加しています。

リモートワーク環境での採用活動も定着し、オンライン面接やバーチャル企業説明会が当たり前になっています。企業側も、リモートでも効果的に働ける環境整備や評価制度の見直しを進めています。
この流れに乗り遅れると、優秀な人材の獲得競争で大きく後れを取る可能性があります。
2. デジタルスキル人材の需要急増
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、ITスキルを持つ人材の需要が爆発的に増加しています。特に注目すべきは、専門的なITエンジニアだけでなく、一般職でもデジタルリテラシーが必須となっている点です。
経済産業省の調査によれば、2030年にはIT人材が最大で約79万人不足すると予測されています。この深刻な人材不足に対応するため、企業はデジタルスキル人材の採用に力を入れています。
転職市場でも、IT系職種の平均給与は他業種を大きく上回り、転職求人倍率も高水準を維持しています。
3. 働き方の多様化と柔軟な雇用形態
正社員一辺倒だった日本の雇用形態も、大きく変化しています。副業・兼業の解禁、フリーランスとの協業、時短勤務やフレックスタイム制の導入など、多様な働き方を認める企業が増加しています。
特に若い世代を中心に、ワークライフバランスを重視し、自分のライフスタイルに合った働き方を求める傾向が強まっています。この変化に対応できない企業は、若手人材の確保が困難になるでしょう。

マイナビキャリアリサーチLabの調査では、今後3ヶ月以内に中途採用活動を行う企業の割合は60.5%に達しており、多様な人材確保に向けた動きが活発化しています。
あなたの会社は、こうした働き方の多様化にどう対応していますか?
4. ダイバーシティ&インクルージョンの重視
ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)への取り組みは、単なる社会的責任ではなく、ビジネス成長の鍵として認識されるようになりました。性別や年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、多様な人材を活かす組織づくりが求められています。
特に女性活躍推進は重要課題となっており、女性採用の促進とフォロー体制の見直しを進める企業が増えています。また、高齢者の就労意欲も高まっており、65歳以上の高齢者を積極的に雇用する企業も増加しています。
多様な人材を受け入れる企業文化の構築は、採用競争力を高めるだけでなく、イノベーションの創出にもつながります。
5. 早期選考・通年採用の増加
従来の新卒一括採用から、早期選考や通年採用へとシフトする企業が増えています。リクルートワークス研究所の「大卒求人倍率調査(2025年卒)」によれば、2025年卒の大卒求人倍率は1.75倍と、2024年卒の1.71倍から0.04ポイント上昇しており、採用競争は一層激化しています。
就職みらい研究所の『就職白書2025』によると、2025年卒採用の面接開始時期は、面接(対面)で「卒業年次前年2月までの累計」が38.6%(前年比+12.6ポイント)、面接(Web)では「卒業年次前年2月までの累計」が49.2%(同+13.8ポイント)と増加し、約半数の企業が採用広報解禁となる3月よりも前に面接を開始しています。
この傾向は2026年卒でさらに加速し、面接(対面)が51.2%(2025年卒差+11.6ポイント)、面接(Web)が61.8%(同+11.0ポイント)と、早期化が進んでいます。
業界別・職種別の採用動向
採用市場の全体傾向を把握したところで、次は業界別・職種別の具体的な動向を見ていきましょう。業界によって人材需要や採用難易度は大きく異なります。自社の業界状況を正確に把握することが、効果的な採用戦略の第一歩です。
厚生労働省の最新データによれば、職業別の有効求人倍率には大きな差があり、人材不足と人材過剰の業界が明確に分かれています。
人材不足が深刻な業界と職種
2025年現在、特に人材不足が深刻な業界と職種は以下の通りです:
- IT・通信業:デジタル化の加速により、エンジニアを中心に深刻な人材不足。転職求人倍率が最も高い業界の一つ。
- 建設・不動産業:土木の職業の有効求人倍率は6.14倍と極めて高く、慢性的な人手不足状態。
- 介護・医療:高齢化社会の進行に伴い、介護関係職種の有効求人倍率は3.41倍と高水準。
- サービス業:コロナ禍からの回復に伴い、サービス業の人材需要が急増。有効求人倍率は2.42倍。
- コンサルティング業:企業の経営課題解決ニーズの高まりにより、コンサルタント人材の需要が増加。

これらの業界では、人材確保のための給与水準の引き上げや福利厚生の充実、採用手法の多様化が進んでいます。
比較的採用しやすい業界と職種
一方で、以下の業界や職種では比較的人材が充足しています:
- 一般事務職:有効求人倍率0.30倍と、求職者が求人数を大きく上回っている状況。
- 会計事務:有効求人倍率0.57倍と、人材過剰の傾向。
- 運搬・清掃・包装等の職業:有効求人倍率0.29倍と、求職者数が多い状況。
これらの職種では、単純な人材確保よりも、いかに質の高い人材を見極め、採用するかが課題となっています。
私は先日、ある中小企業の採用担当者と話す機会がありました。IT人材の採用に苦戦していた彼は、「大手企業との給与競争では勝てない。でも、私たちにしかできない価値提供があるはず」と悩んでいました。
結局彼らは、大手にはない「裁量の大きさ」と「成長スピード」を前面に打ち出した採用戦略に切り替え、優秀なエンジニアの採用に成功したのです。
成功企業に学ぶ採用戦略
厳しい採用環境の中でも、革新的な採用戦略で成果を上げている企業が存在します。そうした成功企業の事例から、実践的なヒントを探ってみましょう。
採用に成功している企業に共通するのは、従来の採用手法にとらわれず、時代の変化に合わせた新しいアプローチを積極的に取り入れている点です。
SNS採用の活用事例
SNSを活用した採用施策は、特に若年層へのリーチに効果を発揮しています。従来の採用媒体では届かなかった潜在的な人材層にアプローチできるのが大きな魅力です。
IT企業A社(従業員数120名)では、エンジニア採用が困難な状況に直面していました。そこでGitHub・QiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告を展開したところ、応募者数が0名から月12名に増加。採用コストを50%削減し、採用期間も3ヶ月から1ヶ月に短縮することに成功しました。

製造業B社(従業員数80名)も、若手人材確保が課題でしたが、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告を活用。20代応募者が2名から月10名に増加し、企業認知度が30%向上、採用成功率も60%向上という成果を上げています。
SNS採用の成功ポイントは、単なる求人情報の発信ではなく、企業の魅力や社員の生の声、職場の雰囲気などを伝えるコンテンツ作りにあります。また、精密なターゲティングにより、年齢、職歴、興味関心など詳細な条件で理想の人材にピンポイントでアプローチできる点も大きな強みです。
アルムナイ採用の広がり
「アルムナイ採用」とは、過去に自社で働いていた元社員(アルムナイ)を再雇用する採用手法です。2025年の採用市場では、このアルムナイ採用が注目を集めています。
元社員は自社の文化や業務を理解しているため、入社後の適応が早く、即戦力として活躍できるメリットがあります。また、外部での経験を持ち帰ることで、新たな視点や知識を組織にもたらす効果も期待できます。
アルムナイ採用を成功させるためには、退職時の関係性維持が鍵となります。退職者とのネットワークを構築し、定期的なコミュニケーションを取ることで、再雇用の可能性を高めることができます。
リファラル採用の効果
「リファラル採用」とは、自社の社員からの紹介で人材を採用する方法です。社員が自分のネットワークから候補者を紹介するため、企業文化との適合性が高く、定着率も良好な傾向があります。
サービス業C社(従業員数200名)では、ブランド認知度の低さが課題でしたが、リファラル採用制度を導入したところ、直接応募が3倍増。応募者の質が大幅に向上し、採用単価も40%削減できました。
リファラル採用を成功させるポイントは、社員が自社を誇りに思い、周囲に推薦したいと感じる環境づくりです。また、紹介制度の報奨金や表彰制度など、社員のモチベーションを高める仕組みも重要です。
あなたの会社では、社員が友人や知人に自社を勧めたくなるような環境が整っていますか?
採用コスト削減と効果最大化の秘訣
採用活動は企業にとって大きなコストです。特に人材不足が深刻化する2025年では、採用コストの高騰が多くの企業の悩みとなっています。しかし、戦略的なアプローチで採用コストを削減しながら、効果を最大化することは可能です。
私が以前関わった中堅企業では、採用予算を前年比20%削減しながらも、採用数を15%増加させることに成功しました。その秘訣は何だったのでしょうか?
データ分析による採用活動の最適化
成功企業に共通するのは、採用活動のデータ分析と継続的な改善サイクルの確立です。応募者数、内定承諾率、採用コスト、入社後のパフォーマンスなど、様々な指標を測定・分析することで、効果的な採用チャネルや採用手法を特定できます。

例えば、SNS採用Proのようなサービスでは、リアルタイムでの効果測定と詳細なデータ分析により、採用活動の効果を可視化し、継続的な改善を実現しています。どの広告がどのターゲット層に効果があるのか、どのメッセージが反応を得やすいのかなど、細かく分析することで、採用予算を最適に配分できます。
データに基づく採用活動の最適化は、単なるコスト削減ではなく、限られた予算で最大の効果を得るための戦略的アプローチです。
採用ブランディングの強化
採用コストを長期的に削減するためには、「採用ブランディング」の強化が欠かせません。採用ブランディングとは、求職者に対して自社の魅力や価値観を一貫して伝え、「働きたい会社」としてのイメージを構築することです。
強い採用ブランドを持つ企業は、採用広告への依存度が低く、自社への直接応募が増加します。また、応募者の質も向上し、採用プロセスの効率化にもつながります。
採用ブランディングの強化には、以下の要素が重要です:
- 明確な企業理念とビジョンの発信
- 社員の生の声や体験談の共有
- 職場環境や社内文化の可視化
- 成長機会やキャリアパスの明示
- 社会貢献活動や企業の取り組みのアピール
これらを一貫して発信することで、求職者の心に響く採用ブランドを構築できます。
採用と定着の一体化
採用コスト削減の観点から見落とされがちなのが、「定着率の向上」です。いくら採用に成功しても、早期に退職されては採用コストが無駄になってしまいます。
就職みらい研究所の調査によれば、初任配属に関する取り組みで「本人のキャリアや成長の観点から、なぜそのポジションに配置されたかを説明している」企業は、採用充足企業で47.4%、未充足企業で39.6%と差が見られます。また、採用充足企業と未充足企業では、働き方の制度やオフィス環境の情報提供の割合、キャリアに関する社内制度の利用状況にも差があります。
つまり、採用活動と入社後のフォローを一体化し、「入社前の期待」と「入社後の現実」のギャップを最小化することが、定着率向上の鍵となります。
具体的には、以下の取り組みが効果的です:
- 採用段階での正確な情報提供(良い面も課題も含めた透明性)
- 入社前研修や内定者フォローの充実
- 入社後のオンボーディングプログラムの強化
- メンター制度やバディ制度の導入
- 定期的な1on1ミーティングの実施
これらの施策により、新入社員の早期戦力化と定着率向上を同時に実現できます。
2025年以降の採用市場予測と対応策
最後に、2025年以降の採用市場がどのように変化していくのか、そして企業はどのように対応すべきかを考えてみましょう。
採用市場の変化は加速しており、今後数年で大きなパラダイムシフトが起こる可能性があります。先見性を持って準備することが、将来の人材確保の鍵となるでしょう。
AI・テクノロジーの採用への影響
採用プロセスにおけるAI・テクノロジーの活用は、今後さらに進化していくでしょう。就職活動においてすでに生成AIを使用した学生の割合は34.5%(前年比+20.0ポイント)と大幅に増加しています。
企業側でも、AI面接ツールやチャットボットの活用、レジュメスクリーニングの自動化など、テクノロジーを駆使した採用効率化が進んでいます。

しかし、テクノロジーの活用は人間の判断を代替するものではなく、人間がより価値の高い判断に集中するための補助ツールと位置づけるべきです。AIが候補者のスキルや経験を評価する一方で、企業文化との適合性や人間性の評価は、依然として人間の直感や経験に頼る部分が大きいでしょう。
テクノロジーと人間の強みを組み合わせたハイブリッド型採用が、2025年以降のスタンダードになると予測されます。
スキルベース採用の台頭
従来の「学歴」や「職歴」重視の採用から、「スキル」や「コンピテンシー」を重視する採用へのシフトが加速しています。特にデジタル人材の採用では、学歴よりも実際の技術力やプロジェクト実績が重視される傾向が強まっています。
この傾向は、労働市場の流動性を高め、キャリアチェンジやリスキリングを促進する効果があります。企業側も、従来の採用基準を見直し、多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れる柔軟性が求められるでしょう。
スキルベース採用を成功させるためには、以下の点が重要です:
- 必要なスキルの明確な定義と評価基準の策定
- スキル評価のための実践的な課題やテストの導入
- ポテンシャル(成長可能性)の評価方法の確立
- 入社後の継続的なスキル開発支援
これらの取り組みにより、真に組織に貢献できる人材を見極め、採用することができます。
持続可能な採用戦略の構築
2025年以降の採用市場を見据えると、短期的な人材確保だけでなく、長期的・持続可能な採用戦略の構築が不可欠です。人口減少が続く日本において、採用難は構造的な問題であり、一時的な対応では解決できません。
持続可能な採用戦略には、以下の要素が含まれます:
- 人材パイプラインの構築:インターンシップや産学連携を通じた早期からの関係構築
- 内部人材の育成・活用:既存社員のリスキリングや社内公募制度の活性化
- 多様な採用チャネルの確保:従来型媒体、SNS、リファラル、アルムナイなど複数の採用経路の確立
- 働き方改革の推進:多様な働き方の受け入れによる採用ターゲットの拡大
- 採用ブランドの継続的な強化:一貫したメッセージと価値提供の発信
これらの要素を組み合わせ、自社の特性に合った持続可能な採用エコシステムを構築することが、2025年以降の人材獲得競争を勝ち抜く鍵となるでしょう。
まとめ:2025年採用成功のための行動計画
2025年の採用市場は、少子高齢化による労働人口の減少、デジタル化の加速、働き方の多様化など、様々な要因により大きく変化しています。この変化に対応し、優秀な人材を確保するためには、従来の採用手法にとらわれない革新的なアプローチが必要です。
本記事で紹介した5大トレンド(リモートワーク対応の強化、デジタルスキル人材の需要急増、働き方の多様化、ダイバーシティ&インクルージョンの重視、早期選考・通年採用の増加)を踏まえ、自社の採用戦略を見直してみましょう。
特に注目すべきは、SNS採用、アルムナイ採用、リファラル採用などの新しい採用手法です。これらを効果的に活用することで、従来の採用手法では届かなかった人材へのアプローチが可能になります。
また、データ分析による採用活動の最適化、採用ブランディングの強化、採用と定着の一体化など、採用コスト削減と効果最大化の施策も重要です。限られた予算で最大の効果を得るためには、戦略的なアプローチが欠かせません。
2025年以降の採用市場を見据えると、AI・テクノロジーの活用、スキルベース採用への移行、持続可能な採用戦略の構築など、長期的な視点での取り組みも重要です。
採用市場の変化は課題でもありますが、同時にチャンスでもあります。従来の常識にとらわれず、革新的な発想で採用に取り組む企業こそが、人材獲得競争を勝ち抜き、持続的な成長を実現できるでしょう。
あなたの会社の採用戦略は、2025年の変化に対応できていますか?今こそ、未来を見据えた採用改革に着手する時です。
SNS採用Proでは、SNS広告と採用施策を組み合わせたサービスを提供し、従来の採用手法では届かなかった人材へのアプローチを可能にします。精密なターゲティング機能、リアルタイムでの効果測定、専任担当者によるサポート体制など、時代の変化に対応した最新の採用手法で、あなたの会社の採用課題解決をサポートします。
詳細はSNS採用Proのウェブサイトをご覧ください。無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。










