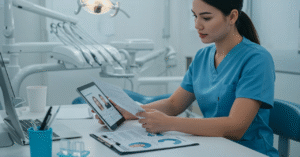介護業界の人材不足は年々深刻化しています。厚生労働省のデータによれば、介護職の有効求人倍率は全職種平均と比較して約3倍もの開きがあるのが現状です。
多くの介護事業者が「求人を出しても応募が集まらない」「採用業務に時間を取られて本来の業務に集中できない」といった課題を抱えています。
特に中小介護事業者にとって、この人材不足は経営の根幹を揺るがす重大な問題となっているのです。
介護業界が直面する採用課題
介護業界の採用市場は非常に厳しい状況にあります。
コロナの影響を受けて全国的に求人倍率が下がっている中でも、介護業界の求人倍率は3倍~4倍と高止まりしています。この数字は、求職者1人に対して3~4件の求人があることを意味し、事業者側からすれば人材獲得競争が極めて激しいことを示しています。
ある関西地方の特別養護老人ホームの人事担当者はこう嘆いていました。「採用業務に週に15時間以上を費やしているのに、なかなか人が集まらない。本来の業務に支障が出ているんです」
中小介護事業者が直面している主な採用課題は以下の通りです。
- 応募者不足:求人を掲載しても応募が集まらない
- 時間不足:採用業務に時間を取られ本業に集中できない
- コスト負担:人材紹介会社の高額な紹介料が経営を圧迫
- ノウハウ不足:効果的な求人媒体の選定方法がわからない
- 業務負担:面接調整や条件交渉などの事務作業が煩雑
- 採用戦略:中小事業者の魅力を効果的にアピールできない
このような状況の中、いかに他の施設との差別化を図り、限られた人材プールの中から優秀な人材を獲得するかが、介護事業者の大きな課題となっています。

差別化戦略1:大手にはない中小ならではの魅力をアピール
大手介護施設との競争で勝ち抜くには、中小事業者ならではの強みを最大限に活かすことが重要です。
中小介護事業者の特性と魅力を深く理解し、大手施設との差別化ポイントを明確にした採用戦略を策定しましょう。アットホームな職場環境や成長機会など、中小事業者ならではの魅力を最大限に活用することで、応募者の心を掴むことができます。
具体的には、以下のような差別化ポイントが効果的です。
アットホームな職場環境の強調
中小介護施設の最大の強みの一つが、アットホームな雰囲気です。大規模施設では実現できない家族的な雰囲気や、スタッフ同士の距離の近さをアピールしましょう。
「うちの施設では、スタッフ全員の顔と名前が一致します。大手のように匿名化された環境ではなく、一人ひとりの個性を大切にしています」
このような温かみのある職場環境は、人間関係を重視する求職者にとって大きな魅力となります。実際に、介護労働安定センターの調査によれば、離職理由の上位には「職場の人間関係に問題があったため」が挙げられています。良好な人間関係を築きやすい環境であることをアピールすることで、長く働きたいと考える人材を引き付けることができるのです。
個人の成長機会の提示
中小規模だからこそ可能な、幅広い業務経験や早期のキャリアアップの機会を強調しましょう。大手では数年かかるようなポジションへの昇進が、中小施設ではより早く実現できる可能性があります。
また、意思決定プロセスへの参加機会や、新しいアイデアを実践できる柔軟性も中小施設の強みです。「あなたのアイデアが明日の施設を変える」といったメッセージは、自己成長を重視する求職者に響きます。
地域密着型サービスの価値
地域に根ざした介護サービスを提供している強みを活かしましょう。地域住民との深いつながりや、地域社会への貢献といった側面は、働きがいを求める人材にとって魅力的です。
九州地方のあるグループホーム管理者は、「地域の方々と顔の見える関係を築けることが、スタッフの大きなやりがいになっています」と語っています。このような地域との結びつきを求人情報で強調することで、単なる仕事以上の価値を提供していることをアピールできます。

差別化戦略2:求人原稿の徹底的な差別化
介護業界の求人は一見すると似たような内容に見えがちです。しかし、求人原稿の書き方一つで応募数に大きな差が生まれます。
求人広告の語尾ひとつで会社の印象が変わるんだと感じました。私が求職者の方々に伝えたかったメッセージも、凝縮されていたと思います。
効果的な求人原稿を作成するためのポイントを見ていきましょう。
魅力的なキャッチコピーの作成
求人のタイトルやキャッチコピーは、求職者の目に最初に飛び込む要素です。ここで興味を引けなければ、詳細な内容まで読んでもらえません。
「未経験歓迎」「資格取得支援あり」といった一般的なフレーズではなく、施設の独自性や価値観を反映したキャッチコピーを考えましょう。例えば、「地域の笑顔を支える、アットホームな介護チーム」「一人ひとりの成長を大切にする介護施設です」など、施設の特徴を端的に表現するフレーズが効果的です。
具体的なエピソードの活用
抽象的な表現よりも、具体的なエピソードの方が求職者の心に残ります。
「先月入社した20代のスタッフは、前職では大規模施設で働いていましたが、『ここでは利用者さん一人ひとりとじっくり向き合える時間があり、やりがいを感じます』と話しています」
このような実際のスタッフの声や具体的なエピソードは、求職者が自分自身をその環境に置き換えて想像しやすくなります。架空のエピソードではなく、実際の事例を用いることで信頼性も高まります。
視覚的要素の効果的活用
文字情報だけでなく、施設の雰囲気が伝わる写真や動画を活用することで、求職者の興味を引き付けることができます。
実際の職場環境や、スタッフが生き生きと働いている様子、チームでの活動風景などを視覚的に伝えることで、「ここで働きたい」という感情を喚起することができます。
関東地方のあるデイサービスでは、スタッフの笑顔や利用者との交流シーンを求人ページに掲載したところ、応募数が1.5倍に増加したという事例があります。
あなたの施設の雰囲気を最も良く表す瞬間はどんな場面ですか?
明確な成長ストーリーの提示
求職者は単に「今」の仕事だけでなく、将来のキャリアパスにも関心を持っています。入社後のキャリアステップを明確に示すことで、長期的な展望を持って応募してもらうことができます。
「入社1年目:基本的な介護技術の習得と資格取得支援、3年目:リーダー職への挑戦機会、5年目:マネジメント職への道」といった具体的なキャリアパスを示すことで、成長意欲の高い人材を惹きつけることができます。

差別化戦略3:積極的スカウト活動の導入
待ちの採用から攻めの採用へ。これが介護人材獲得の新たなトレンドです。
従来の求人広告掲載による「待ち」の姿勢から脱却し、積極的に求職者にアプローチする「攻め」の採用戦略を導入することで、採用成功率を大幅に高めることができます。
スカウト活動は、単に応募を待つのではなく、自ら優秀な人材を見つけ出し、直接コンタクトを取る方法です。この戦略が特に効果を発揮するのが介護業界なのです。
個別カスタマイズしたスカウト
転職サイトのスカウト機能を活用する際は、テンプレートメッセージではなく、一人ひとりの経歴や特性に合わせたカスタマイズメッセージを送ることが重要です。
「あなたの〇〇での経験が、私たちの施設でも活かせると思いました」など、相手の経歴を具体的に言及することで、「自分のことをしっかり見てくれている」という印象を与えることができます。
実際にエン転職のスカウト機能を活用した事例では、IT業界経験者をターゲットとしたスカウトを送るというアプローチが効果を上げています。業界の枠を超えた視点で人材を発掘することも、差別化の一つの方法なのです。
継続的な候補者フォロー
一度のコンタクトで反応がなかった場合でも、諦めずに継続的なフォローを行うことが大切です。
「前回ご連絡した際はタイミングが合わなかったかもしれませんが、当施設では引き続き素晴らしい人材を求めています」といった形で、定期的に状況確認のメッセージを送ることで、求職者の転職タイミングと合致する可能性が高まります。
人は平均して7回のコンタクトで初めて行動を起こすと言われています。粘り強くアプローチすることが、採用成功への鍵となるのです。
高い返信率を実現する工夫
スカウトメッセージの返信率を高めるには、メッセージの内容だけでなく、送信のタイミングや頻度にも工夫が必要です。
平日の夜間や週末など、求職者がメッセージを確認しやすい時間帯を狙って送信することで、開封率と返信率を高めることができます。また、文面は簡潔で読みやすく、具体的なアクションを明示することも重要です。
「ご興味があれば、まずは施設見学だけでもいかがでしょうか?」など、ハードルの低い次のステップを提案することで、返信を促すことができます。
スカウト活動は単なる求人情報の発信ではなく、求職者との対話の始まりです。どのようなコミュニケーションを心がけていますか?

差別化戦略4:採用プロセスの効率化と応募者体験の向上
応募者を惹きつけるには、採用プロセス自体も重要な差別化ポイントになります。
採用プロセスがスムーズで応募者に配慮されていると感じてもらえれば、それだけで「この施設は従業員を大切にしている」という印象を与えることができます。
実際、応募から面接、内定までのプロセスで感じた印象が、入職後の定着率にも大きく影響するのです。
迅速なレスポンス
応募者からの連絡や応募に対して、できるだけ早く返信することが重要です。24時間以内の返信を心がけましょう。
「お問い合わせいただきありがとうございます。担当の○○です。ご質問について明日までにご回答いたします」といった形で、まずは受け取った旨を伝えるだけでも印象が大きく変わります。
人材不足の介護業界では、優秀な人材は複数の施設に同時に応募していることが多いため、レスポンスの速さが採用成功の鍵となります。
柔軟な面接設定
介護職の求職者の中には、現職との兼ね合いで平日の日中に面接に来ることが難しい人も少なくありません。夕方以降や週末の面接枠を設けるなど、応募者の都合に合わせた柔軟な対応を行いましょう。
また、オンライン面接の選択肢を用意することも、応募のハードルを下げる効果があります。特に遠方の応募者や、忙しいスケジュールの中で転職活動をしている人にとっては大きなメリットとなります。
「応募者の時間を大切にする」という姿勢は、「従業員を大切にする職場である」という印象につながります。
施設見学・体験シフトの活用
面接だけでは伝わらない職場の雰囲気や実際の業務内容を知ってもらうため、施設見学や短時間の体験シフトを取り入れることも効果的です。
「百聞は一見にしかず」というように、実際に職場を見て、スタッフと交流することで、応募者は自分がその環境に馴染めるかどうかを具体的にイメージすることができます。
同時に、施設側も応募者の現場での様子や利用者との接し方を観察することができ、相互理解を深める貴重な機会となります。
採用のミスマッチを減らし、入職後の定着率を高めるためにも、このようなリアルな体験機会を提供することは非常に重要です。
丁寧なフィードバック
不採用となった応募者に対しても、可能な限り具体的なフィードバックを提供することで、応募者に対する誠実さを示すことができます。
「今回は他の方に決まりましたが、あなたの○○というスキルや経験は素晴らしいと感じました。今後機会があれば、ぜひまたご応募ください」といった前向きなメッセージは、応募者の心象を良くし、将来的な再応募や口コミにもつながります。
採用プロセスは、応募者があなたの施設について初めて深く知る機会です。その体験がポジティブなものであれば、たとえ今回は採用に至らなくても、将来の応募や良い評判につながるのです。
差別化戦略5:福利厚生と働き方の柔軟性
給与面での競争が難しい中小介護事業者にとって、福利厚生や働き方の柔軟性は大きな差別化ポイントになります。
「働きやすさ」という観点から、大手にはない独自の福利厚生や柔軟な勤務体制を整えることで、応募者を惹きつけることができるのです。
特に介護業界では、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっており、単純な給与額だけでなく「総合的な働きやすさ」が重視されています。
独自の福利厚生制度
大手では実現しにくい、施設独自の福利厚生制度を検討してみましょう。例えば、誕生日休暇、リフレッシュ休暇、家族の記念日休暇など、スタッフの生活に寄り添った休暇制度は喜ばれます。
また、地域の商店街と提携した割引制度や、施設の車両を休日に利用できる制度など、地域密着型だからこそ可能な福利厚生も差別化につながります。
「当施設では、スタッフの心身の健康を最も大切にしています。そのため、毎月1日の『心身リフレッシュデー』には、希望するスタッフに優先的に休暇を取得してもらっています」
このような独自の取り組みは、求職者に「ここで働きたい」と思わせる強力な動機づけになります。
柔軟な勤務体制
介護職は女性が多く、育児や家庭との両立を重視する方も少なくありません。短時間勤務、時差出勤、選択制シフトなど、個人のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務体制を整えることで、幅広い人材を惹きつけることができます。
「学校行事には必ず参加できるようシフトを調整します」「急な子どもの病気にも対応できるバックアップ体制があります」といった具体的な配慮は、特に子育て世代の求職者に強くアピールします。
実際、育児・介護休業法の改正により、仕事と介護の両立支援制度も整備されてきていますが、法定以上の柔軟な対応ができる職場環境は大きな魅力となります。
キャリアアップ支援
資格取得支援や外部研修への参加費用補助など、スタッフの成長を支援する制度も重要な福利厚生です。
「介護福祉士の資格取得を目指す方には、試験対策講座の費用全額を施設が負担します」「認知症ケア専門士など、専門資格の取得者には資格手当を支給しています」
このようなキャリアアップ支援は、単に現在の待遇だけでなく、将来的な成長や収入アップの可能性を示すことになり、向上心のある人材を惹きつける効果があります。
あなたの施設では、スタッフの「働きやすさ」をどのように実現していますか?

差別化戦略6:人材紹介会社との戦略的パートナーシップ
人材紹介会社の活用は、高額な紹介料がネックになると考える介護事業者も少なくありません。
しかし、適切な人材紹介会社と戦略的なパートナーシップを結ぶことで、効率的な人材獲得が可能になります。
特に中小介護事業者の価値を理解した紹介会社から、質の高い人材を継続的に紹介してもらうことで、採用の質と量を両立させることができるのです。
厳選された紹介会社との連携
すべての人材紹介会社が介護業界、特に中小介護事業者の特性を理解しているわけではありません。介護業界に強みを持ち、中小事業者の特性や魅力を理解している紹介会社を厳選することが重要です。
紹介会社選びのポイントとしては、過去の介護業界での紹介実績、担当者の介護業界への理解度、中小事業者への紹介実績などを確認しましょう。
「私たちは単なる人材の仲介ではなく、介護事業者様の経営課題解決のパートナーでありたいと考えています」と語る紹介会社は、長期的な関係構築が期待できます。
中小事業者特化の提案依頼
人材紹介会社に対しては、単に「介護職員を紹介してほしい」という漠然とした依頼ではなく、自施設の特徴や魅力、求める人材像を具体的に伝え、中小事業者ならではの魅力を活かした提案を依頼しましょう。
「大手施設ではなく、地域密着型の小規模施設で働くことに価値を見出せる人材を紹介してほしい」「利用者一人ひとりとじっくり向き合いたいと考えている人材を優先的に紹介してほしい」など、具体的な要望を伝えることで、マッチング精度が高まります。
継続的な人材供給体制の構築
単発の採用ではなく、中長期的な人材確保の視点から、紹介会社との関係を構築することが重要です。
定期的な情報交換や施設見学の受け入れなどを通じて、紹介会社の担当者に自施設の魅力や特徴を深く理解してもらうことで、より適切な人材を紹介してもらえる可能性が高まります。
「毎月1回、紹介会社の担当者に施設の近況や採用状況を共有し、今後の採用計画について相談しています」という継続的なコミュニケーションが、効果的な人材紹介につながります。
人材紹介会社は単なる「仲介者」ではなく、あなたの施設の「採用パートナー」です。どのような関係を築いていきたいですか?
差別化戦略7:採用業務の完全代行サービスの活用
採用業務に多くの時間を費やしながらも思うような成果が出ない。これは多くの中小介護事業者が抱える悩みです。
採用業務の大部分を外部に委託することで、施設内の採用担当者の負担を大幅に軽減できます。「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用代行サービスを活用すれば、求人戦略の策定から応募者対応、面接調整まで一貫してサポートを受けられます。
このようなサービスの最大のメリットは、本来の業務に集中できることです。
採用業務の時間削減効果
採用業務は、求人原稿の作成、求人媒体の選定と掲載手続き、応募者対応、面接日程調整、選考プロセス管理など、多岐にわたります。これらの業務を代行サービスに委託することで、大幅な時間削減が可能になります。
関西地方のある特別養護老人ホーム(従業員45名)では、採用代行サービスを導入した結果、採用業務に費やす時間が週15時間から7時間に短縮されました。人事担当者は「採用業務の負担が大幅に軽減され、本来の業務に集中できるようになりました」と語っています。
この時間削減効果は、特に専任の採用担当者がいない中小介護施設にとって、非常に大きなメリットとなります。
専門知識とネットワークの活用
採用代行サービスの多くは、介護業界の採用に特化した専門知識と広範なネットワークを持っています。最新の採用トレンドや効果的な求人媒体、応募者心理など、専門的な知見を活かした採用戦略を提案してもらえます。
「介護業界経験10年以上の採用コンサルタント」「人材紹介業界経験5年以上のスカウト専門スタッフ」など、専門性の高いスタッフによるサポートは、自社だけでは実現困難な採用効果をもたらします。
また、全国の優良人材紹介会社とのネットワークを活用することで、より広範な人材プールにアクセスすることも可能になります。
コスト効率の向上
一見すると追加コストに思える採用代行サービスですが、長期的に見れば採用コストの削減につながることも少なくありません。
人材紹介会社の紹介料(一般的に年収の30~35%程度)と比較すると、月額定額制の採用代行サービスは、複数名の採用に成功した場合にコスト効率が高まります。
例えば、「かいごのおたすけ採用隊」は月額10万円(税別・契約期間3ヶ月〜)で採用業務を完全代行し、初期費用無料、成果報酬無料、求人掲載費込みの明確な料金体系を提供しています。関東地方のあるデイサービス(従業員15名)では、このサービスを利用して3ヶ月で5名の採用に成功しました。
採用業務の効率化と質の向上を同時に実現できる採用代行サービスは、限られたリソースで最大の採用効果を目指す中小介護事業者にとって、強力な味方となるでしょう。
差別化戦略8:採用後のフォローアップ体制の充実
採用活動の成功は、優秀な人材の獲得だけでは終わりません。入職後の定着率を高めることが、真の採用成功と言えるでしょう。
介護業界の離職率の高さを考えると、採用後のフォローアップ体制の充実は、差別化戦略として非常に重要です。
新入職員が安心して働き続けられる環境を整えることで、採用コストの削減と組織の安定化を同時に実現できるのです。
充実した研修制度
新入職員が不安なく業務に取り組めるよう、段階的な研修プログラムを用意することが重要です。特に未経験者や久しぶりに職場復帰する人にとって、初期の研修体制は大きな安心材料となります。
「最初の1週間は先輩スタッフがマンツーマンでサポートします」「3ヶ月間は段階的に業務範囲を広げていくプログラムを用意しています」など、具体的な研修体制を示すことで、入職後の不安を軽減できます。
また、定期的なフォローアップ研修や、個別の成長に合わせたスキルアップ研修なども、長期的な定着を促進します。
メンター制度の導入
新入職員一人ひとりに先輩スタッフをメンターとして付ける制度は、業務上の疑問だけでなく、職場環境や人間関係の悩みなども相談できる環境を作ります。
「仕事の相談はもちろん、職場での人間関係や将来のキャリアについても気軽に相談できる先輩がいることで、新入職員の不安が大きく軽減されます」
メンターは直属の上司とは別の立場であることが望ましく、より自由に相談できる関係性を構築できます。
定期的な面談とフィードバック
入職後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など、定期的な面談の機会を設けることで、新入職員の不安や課題を早期に発見し、対応することができます。
「どんな小さな悩みでも遠慮なく話してください。一緒に解決策を考えましょう」という姿勢で臨むことで、新入職員は「自分の声が届く職場」という安心感を得られます。
また、良い点は積極的に評価し、改善点は具体的なアドバイスとともに伝えることで、成長を促進することができます。
職場の人間関係構築支援
介護労働安定センターの調査によれば、離職理由の上位に「職場の人間関係に問題があったため」が挙げられています。良好な人間関係の構築は、定着率向上の鍵となります。
新入職員歓迎会、チーム単位での食事会、レクリエーション活動など、業務外でのコミュニケーション機会を意図的に設けることで、職場の人間関係構築を支援しましょう。
「月に一度、『ティータイムミーティング』と称して、お菓子を囲みながらカジュアルに意見交換する時間を設けています。この場では役職関係なく、自由に発言できるルールにしています」
このような取り組みは、新入職員が職場に溶け込むきっかけとなり、長期的な定着につながります。
採用は「入口」に過ぎません。真の採用成功は「定着」で測られます。あなたの施設では、新入職員をどのようにサポートしていますか?
まとめ:差別化戦略で介護人材獲得競争を勝ち抜く
介護業界の人材不足が深刻化する中、従来の採用方法だけでは十分な人材を確保することが難しくなっています。特に中小介護事業者にとって、大手施設との差別化は採用成功の鍵となります。
本記事で紹介した8つの差別化戦略を実践することで、限られたリソースの中でも効果的な採用活動を展開し、優秀な人材を獲得することが可能です。
中小だからこそできる「アットホームな職場環境」「個人の成長機会」「地域密着型サービス」などの強みを最大限に活かし、求職者の心に響く求人情報を発信しましょう。
また、積極的スカウト活動や採用プロセスの効率化、充実した福利厚生、採用業務の代行サービス活用など、複合的なアプローチで採用力を高めることが重要です。
採用活動は一朝一夕で成果が出るものではありません。中長期的な視点で戦略的に取り組むことで、持続可能な採用体制を構築することができます。
介護人材の獲得競争は今後も続きますが、自施設の強みを活かした差別化戦略を実践することで、この競争を勝ち抜くことができるでしょう。
介護人材の採用でお悩みの方は、中小介護事業者専門の採用課題解決サービス「かいごのおたすけ採用隊」にご相談ください。月額10万円(税別・契約期間3ヶ月〜)で採用業務を完全代行し、中小事業者ならではの魅力を最大限に活かした採用戦略をご提案します。初期費用無料、成果報酬無料、求人掲載費込みの明確な料金体系で、安心してご利用いただけます。
詳細はかいごのおたすけ採用隊のウェブサイトをご覧いただくか、無料相談をご利用ください。あなたの施設の採用課題解決をサポートします。