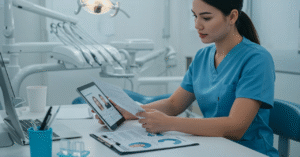介護業界における人材不足の現状と課題
介護業界の人材不足は、年々深刻さを増しています。厚生労働省の発表によると、2026年度には約240万人(2022年度比で約25万人増)、2040年度には約272万人(同約57万人増)の介護職員が必要になると推計されています。
この数字を見ると、今後も継続的に多くの人材を確保していかなければならないことが分かります。
しかし現場では、すでに人手不足による様々な問題が発生しています。介護サービス提供事業者の63.0%が「人手不足を感じている」と回答し、特に訪問介護員については80.6%もの事業者が人材不足を実感しているのです。

現場で働く従業員自身も「人手が足りない」という悩みを抱えており、全体の52.3%がこの問題を指摘しています。
では、なぜこれほどまでに介護業界の人材確保が難しくなっているのでしょうか?
介護業界で人材不足が深刻化する7つの原因
介護業界における人材不足の背景には、複数の要因が絡み合っています。特に以下の7つの原因が大きく影響しています。
これらの要因を理解することは、効果的な解決策を見出すための第一歩となるでしょう。少子高齢化による労働力の減少と介護需要の増加という構造的な問題から、業界特有の課題まで幅広く見ていきましょう。
1. 少子高齢化による労働力の減少
日本の高齢化率は2021年時点で28.9%に達しています。総人口は減少している一方で、65歳以上の人口は増加の一途をたどっているのです。
これは介護業界にとって二重の問題を引き起こしています。労働力となる若年層が減少する一方で、介護サービスを必要とする高齢者が増えているのです。
2021年の出生数は約81万人で、2015年と比較すると約19万人も減少しています。この傾向は今後も続くと予想され、労働力の確保がますます難しくなるでしょう。
2. 介護職のネガティブイメージ
介護職に対するネガティブなイメージも、人材確保を難しくしている要因の一つです。
介護職非従事者へのアンケート調査によると、介護業界への就業をためらう理由として「体力的にきつい仕事が多い」(49.8%)、「精神的にきつい仕事が多い」(41.8%)、「給与水準が低め」(31.2%)といった回答が多く見られます。

「きつい割に給料が低い」というイメージが定着してしまっていることが、新規参入を妨げる大きな壁となっているのです。
3. 同業他社との採用競争の激化
介護業界内での人材獲得競争も激しくなっています。介護サービス提供事業者の53.1%が「同業他社との人材獲得競争が厳しい」と回答しています。
生産年齢人口が減少する中で、限られた人材を奪い合う状況が生まれているのです。
さらに、介護業界だけでなく、他業種も含めた人材獲得競争が激化していることも大きな課題です。売り手市場の中で、介護業界への人材流入が少なくなっているのです。
4. 労働環境と処遇の問題
介護職の労働環境や処遇も大きな課題です。長時間労働、夜勤、身体的負担の大きさなどが、離職率の高さにつながっています。
また、賃金水準も他業種と比較して低い傾向にあります。責任の重さや業務の難しさに見合った報酬が得られないと感じる職員も少なくありません。
このような労働環境と処遇の問題が、人材確保と定着の両面で大きな障壁となっているのです。
5. 採用ノウハウの不足
特に中小規模の介護事業者では、効果的な採用活動を行うためのノウハウや専門知識が不足していることが多いです。
どのような採用チャネルを活用すべきか、求職者に魅力を伝えるための求人設計をどうすればよいかなど、採用のプロフェッショナルとしてのスキルが十分でないケースが見られます。
採用業務に割ける時間や人員も限られており、効率的な採用活動が行えていないことも課題です。
6. 介護職のキャリアパスの不明確さ
介護職のキャリアパスが不明確なことも、人材確保を難しくしている要因です。
将来的にどのようなキャリアを築けるのか、どのようなスキルアップの機会があるのかが見えにくいため、長期的な展望を持ちにくい職種だと認識されがちです。
特に若年層の求職者は、将来のキャリア展望を重視する傾向があるため、この点が採用の障壁となっています。
7. 業務負担の増加と効率化の遅れ
介護業務の複雑化や書類作成などの事務作業の増加も、現場の負担を増大させています。
また、業務効率化のためのIT活用やデジタル化が他業種に比べて遅れている面もあり、限られた人材で効率的にサービスを提供することが難しくなっています。
この業務負担の増加が、さらなる人材不足を招くという悪循環に陥っているのです。
介護職の人材不足を解決する7つの効果的戦略
ここからは、介護職の人材不足を解決するための7つの効果的な戦略について詳しく見ていきましょう。
これらの戦略は、厚生労働省の取り組みや先進的な介護事業者の成功事例をもとに、実践的かつ効果的なアプローチをまとめたものです。自施設の状況に合わせて取り入れることで、人材確保と定着の両面から課題解決を図ることができるでしょう。
1. 戦略的な求人設計と差別化
効果的な人材確保のためには、他の施設との差別化を図る戦略的な求人設計が不可欠です。特に中小規模の介護事業者は、大手にはない魅力をアピールすることが重要です。
アットホームな職場環境、個々の職員に合わせた柔軟な働き方、成長機会の提供など、自施設ならではの強みを明確にし、それを求人情報に反映させましょう。

また、求職者が本当に知りたい情報(具体的な業務内容、シフト例、教育体制など)を詳細に記載することで、ミスマッチを防ぎ、入職後の早期離職を減らすことができます。
どうですか?自施設の求人情報は、他と差別化できていますか?
2. 多様な採用チャネルの活用
人材確保のためには、複数の採用チャネルを効果的に組み合わせることが重要です。従来の求人サイトや求人広告だけでなく、SNSやリファラル採用(従業員紹介)、地域イベントなど、多様なチャネルを活用しましょう。
特に効果的なのが「待ちの採用」から「攻めの採用」への転換です。潜在的な求職者に対して積極的にアプローチするスカウト活動を取り入れることで、通常の求人では届かない層にもリーチすることができます。
また、地域の教育機関との連携も重要な採用チャネルとなります。介護福祉士養成校や高校との関係構築を通じて、若年層の採用パイプラインを作ることができるでしょう。
3. 労働環境と処遇の改善
人材の確保と定着のためには、労働環境と処遇の改善が不可欠です。具体的には、以下のような取り組みが効果的です。
- 柔軟な勤務形態の導入(短時間勤務、時差出勤、週休3日制など)
- キャリアパスと連動した賃金体系の整備
- 業務効率化による負担軽減
- 休憩時間の確保や有給休暇取得の促進
- 子育て・介護との両立支援
厚生労働省も「労働環境・処遇の改善」を介護人材確保の重要な柱として位置づけており、様々な支援策を展開しています。
労働環境の改善は一朝一夕にはいきませんが、職員の声を聞きながら少しずつ改善を進めることで、職場の魅力向上と定着率の向上につながるでしょう。
4. 教育・研修体制の充実
介護職員の成長を支える教育・研修体制の充実も、人材確保と定着の両面で効果を発揮します。
厚生労働省は「介護に関する入門的研修」を推進しており、介護未経験者の参入を促進するための取り組みを行っています。この制度を活用することで、未経験者でも安心して介護の仕事に就けるようサポートすることができます。

また、施設内での段階的な教育プログラムやキャリアラダー(段階的な成長モデル)の整備、外部研修への参加支援なども重要です。職員が成長を実感できる環境を整えることで、モチベーションの向上と定着率の向上につながります。
特に若手職員には、メンター制度などを通じて丁寧な育成を行うことで、早期離職を防ぐ効果が期待できます。
5. テクノロジーの活用による業務効率化
介護業界でも、テクノロジーの活用による業務効率化が進んでいます。介護記録ソフトやコミュニケーションツール、見守りセンサーなどのICT機器、介護ロボットなどを導入することで、業務負担の軽減と質の向上を同時に実現することができます。
業務効率化により、職員一人ひとりの負担が軽減されれば、限られた人材でもより良いサービスを提供することが可能になります。また、身体的負担の軽減は職員の健康維持にもつながり、長く働き続けられる環境づくりに貢献します。
テクノロジー導入の際は、現場の声をよく聞き、実際の業務フローに合ったものを選定することが重要です。また、導入後のフォローアップや活用促進のための取り組みも欠かせません。
6. 外国人材の活用
人材確保の選択肢として、外国人材の活用も重要な戦略の一つです。EPA(経済連携協定)、技能実習制度、特定技能制度など、様々な制度を通じて外国人介護人材を受け入れることができます。
外国人材の受け入れには、言語や文化の違いによるコミュニケーション課題や、受け入れ体制の整備など、準備すべき点も多くあります。しかし、丁寧な受け入れ準備と育成を行うことで、貴重な戦力として活躍してもらうことが可能です。
特に、日本語教育や生活支援、職場への適応サポートなど、包括的な支援体制を整えることが成功のカギとなります。また、外国人材と日本人職員が互いに学び合える環境づくりも大切です。
7. 専門的な採用支援サービスの活用
採用活動に十分なリソースを割けない事業者にとって、専門的な採用支援サービスの活用は効果的な選択肢となります。
例えば「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用課題解決サービスを利用することで、採用業務を効率化しながら成果を上げることができます。

こうしたサービスでは、求人戦略の策定から求人掲載、スカウト活動、応募者対応、面接調整、条件交渉まで、採用プロセス全体をサポートしてくれます。専門知識を持ったコンサルタントが伴走することで、自社だけでは難しい効果的な採用活動が可能になるのです。
特に中小規模の事業者では、採用にかけられる時間や人員が限られていることが多いため、このようなサービスを活用することで本来の介護業務に集中しながら、効果的な採用活動を行うことができます。
成功事例に学ぶ人材確保のポイント
介護職の人材確保に成功している事業者は、どのような取り組みを行っているのでしょうか。ここでは、実際の成功事例から学ぶべきポイントを紹介します。
これらの事例は、規模や地域は異なっても、共通して「職場の魅力向上」と「効果的な採用活動」の両輪で取り組んでいることが特徴です。自施設の状況に合わせて参考にしてみてください。
関東地方のデイサービスの事例
従業員15名の小規模デイサービスでは、大手施設との差別化を図るため、アットホームな職場環境と個々の職員の成長機会を重視した採用戦略を展開しました。
具体的には、求人情報に「少人数だからこそできるきめ細かなケア」「一人ひとりの意見が運営に反映される風通しの良さ」などの魅力を具体的なエピソードとともに掲載。また、未経験者向けの丁寧な教育体制や、子育て中のスタッフへの柔軟なシフト対応なども明記しました。
さらに、採用支援サービス「かいごのおたすけ採用隊」を活用し、専門スタッフによる積極的なスカウト活動を展開。その結果、3ヶ月で5名の採用に成功し、人手不足を解消することができました。
この事例のポイントは、小規模ならではの魅力を明確にし、それを効果的に伝えるための専門的なサポートを活用した点にあります。
関西地方の特別養護老人ホームの事例
従業員45名の特別養護老人ホームでは、採用業務の負担が大きく、本来の介護業務に支障が出ていました。そこで、採用業務を外部委託することで、業務効率化と採用成果の向上を同時に実現しました。
採用支援サービスの導入により、求人戦略の策定から応募者対応、面接調整まで一貫してサポートを受けることで、採用業務にかかる時間を50%削減。空いた時間を利用して職員の教育や労働環境の改善に注力することができました。
また、採用と並行して、ICT機器の導入による記録業務の効率化や、キャリアパスの明確化による職員のモチベーション向上にも取り組んだことで、新規採用だけでなく既存職員の定着率も向上させることに成功しています。
この事例のポイントは、採用業務の効率化によって生まれた時間とリソースを、職場環境の改善に振り向けた点にあります。採用と定着の好循環を生み出すことができたのです。
九州地方のグループホームの事例
従業員8名の小規模グループホームでは、地域密着型の採用活動と、中小事業者ならではの魅力発信に力を入れました。
地域の介護福祉士養成校との連携強化や、地域イベントへの積極的な参加を通じて施設の認知度を高める取り組みを実施。また、「かいごのおたすけ採用隊」のサポートを受けながら、小規模施設ならではの「利用者一人ひとりとじっくり向き合える環境」「職員同士の距離が近く、意思決定が早い組織風土」などの魅力を効果的に発信しました。
その結果、2ヶ月で2名の採用に成功。小規模ながらも、地域に根差した採用活動と、施設の強みを活かした差別化戦略が功を奏した事例です。
この事例のポイントは、規模の小ささをデメリットではなく、むしろ強みとして捉え直し、それを効果的に発信した点にあります。
人材不足解消に向けた具体的なアクションプラン
ここまで紹介してきた戦略や成功事例を踏まえて、介護職の人材不足解消に向けた具体的なアクションプランを考えてみましょう。
自施設の状況に合わせて、短期的に取り組めることと中長期的な課題を整理し、段階的に実行していくことが重要です。
短期的に取り組むべきこと(1〜3ヶ月)
まずは、比較的短期間で取り組める施策から始めましょう。
- 自施設の強みと弱みを分析し、差別化ポイントを明確にする
- 求人情報の見直しと改善(具体的な業務内容、シフト例、教育体制などを詳細に記載)
- 複数の採用チャネルの活用(求人サイト、SNS、リファラル採用など)
- 職員の声を聞く機会を設け、改善すべき労働環境の課題を洗い出す
- 採用支援サービスの検討と導入
特に求人情報の見直しは、すぐに着手できる重要な施策です。現在の求人情報が求職者にとって魅力的か、必要な情報が十分に盛り込まれているか、再確認してみましょう。
中期的に取り組むべきこと(3ヶ月〜1年)
短期施策と並行して、中期的な視点での取り組みも進めていきましょう。
- 教育・研修体制の整備(段階的な成長プログラム、メンター制度など)
- 労働環境の改善(柔軟な勤務形態の導入、休憩時間の確保など)
- ICT機器や介護ロボットの導入による業務効率化
- キャリアパスと連動した賃金体系の整備
- 地域の教育機関との連携強化
これらの施策は、すぐに結果が出るものではありませんが、中長期的な人材確保と定着に大きく貢献します。計画的に取り組んでいきましょう。
長期的な視点での取り組み(1年以上)
長期的な視点では、組織文化や業界イメージの変革に取り組むことも重要です。
- 介護職の社会的評価向上に向けた情報発信
- 外国人材受け入れ体制の整備
- 組織理念や価値観の浸透による一体感の醸成
- 地域社会との連携強化(地域イベントへの参加、ボランティア受け入れなど)
- 働きがいのある職場づくりと情報発信
これらの取り組みは、単に人材を確保するだけでなく、介護業界全体の魅力向上にもつながる重要な施策です。
人材不足の解消は一朝一夕には実現できませんが、短期・中期・長期の視点でバランスよく取り組むことで、着実に成果を上げることができるでしょう。
まとめ:持続可能な介護現場のために
介護職の人材不足は、少子高齢化という構造的な問題に加え、介護職のイメージや労働環境、採用競争の激化など、様々な要因が複雑に絡み合った課題です。
しかし、本記事で紹介した7つの戦略を効果的に組み合わせることで、人材確保と定着の両面から課題解決を図ることができます。
- 戦略的な求人設計と差別化
- 多様な採用チャネルの活用
- 労働環境と処遇の改善
- 教育・研修体制の充実
- テクノロジーの活用による業務効率化
- 外国人材の活用
- 専門的な採用支援サービスの活用
特に中小規模の介護事業者にとっては、限られたリソースの中で効果的な採用活動を行うことが課題となりますが、「かいごのおたすけ採用隊」のような専門的な採用支援サービスを活用することで、採用業務の負担軽減と成果向上を同時に実現することができます。
介護業界の人材不足解消は、個々の事業者の努力だけでなく、業界全体、さらには社会全体で取り組むべき重要な課題です。しかし、まずは自施設でできることから一つずつ取り組んでいくことが、持続可能な介護現場づくりの第一歩となるでしょう。
人材不足に悩む介護事業者の皆様、ぜひこの記事で紹介した戦略を参考に、自施設に合った人材確保・定着の取り組みを始めてみてください。
介護の仕事の素晴らしさと意義を社会に広め、多くの人が誇りを持って働ける業界にしていくために、一緒に取り組んでいきましょう。
介護人材の採用でお悩みなら、中小介護事業者専門の採用課題解決サービス「かいごのおたすけ採用隊」にご相談ください。月額10万円で採用業務を完全代行し、あなたの施設の魅力を最大限に活かした採用戦略をご提案します。詳細はこちらから