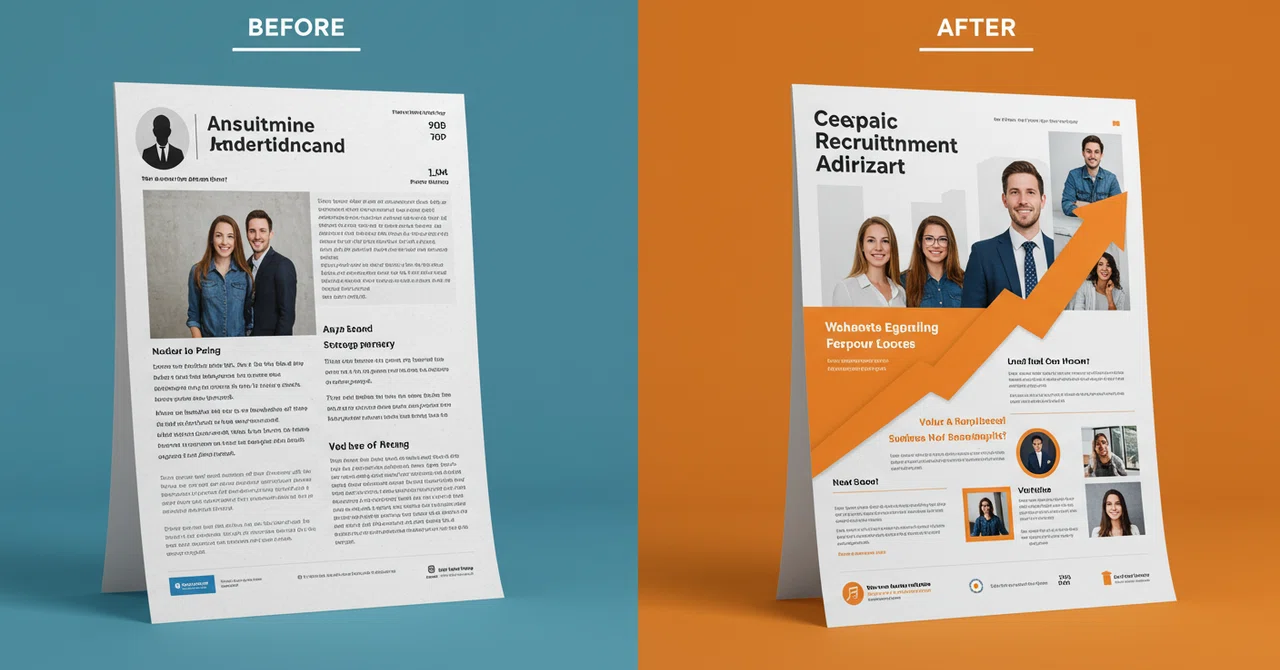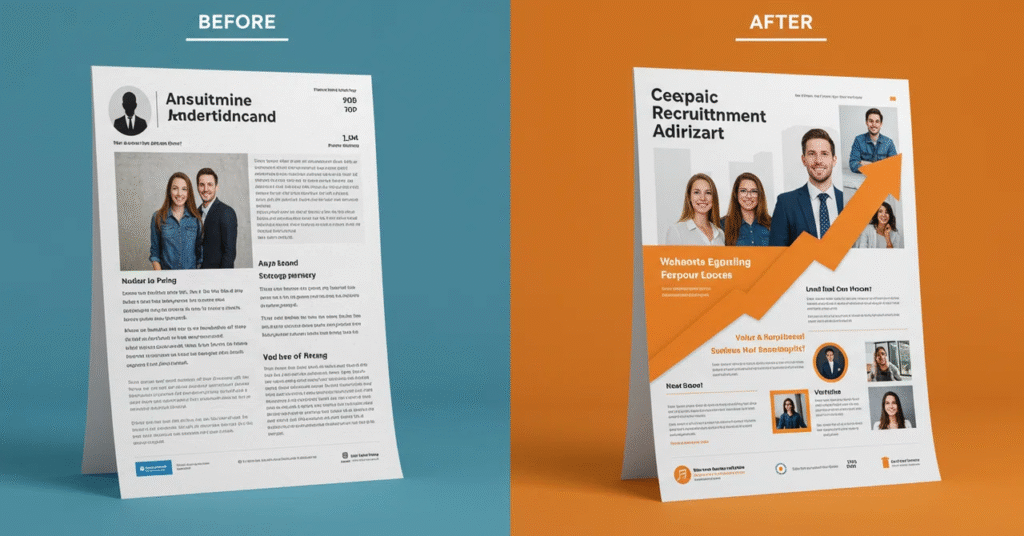
採用広告の改善で応募者数が3倍に!成功の秘訣とは
「求人広告を出しているのに、なぜ応募が集まらないんだろう…」
採用担当者なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。実は、採用広告の「見せ方」を少し工夫するだけで、応募数が劇的に変わることがあります。同じ求人内容でも、表現方法を変えるだけで応募者数が3倍になった企業も珍しくありません。
本記事では、採用広告のBefore/After改善事例を10個ご紹介します。これらの事例から、応募者の心を掴む採用広告の作り方のポイントを学んでいきましょう。
事例1:キャッチコピーの改善で未経験応募者が2倍に
最初に紹介するのは、介護業界の求人広告です。
未経験者を積極採用したい企業にとって、キャッチコピーは非常に重要です。適切なキャッチコピーに変えるだけで、応募者の数が大きく変わることがあります。

Before:専門的すぎるキャッチコピー
「【正社員:介護ヘルパー 〇〇駅】あなたのスキルが活かせます!」
このキャッチコピーでは、「スキル」という言葉が使われています。未経験者にとって、「スキルがない」と感じさせてしまい、応募のハードルを上げてしまっていました。
どう思いますか?あなたが未経験者なら、このコピーを見て「自分には関係ない」と思ってしまいませんか?
After:未経験者に寄り添ったキャッチコピー
「介護職(正社員)未経験でも心配なし!充実の研修あり」
改善後のコピーでは、「未経験でも心配なし」と明確に伝え、さらに「充実の研修あり」と不安を解消する要素を加えました。
この変更だけで、未経験者からの応募が約2倍に増加しました。未経験者の最大の不安は「できるだろうか」という点。その不安を解消するキャッチコピーが効果的だったのです。
事例2:仕事内容の具体化でミスマッチが半減
次に紹介するのは、IT企業のエンジニア採用の事例です。
採用のミスマッチを減らすためには、仕事内容を具体的に伝えることが重要です。曖昧な表現は応募者の想像に任せることになり、入社後のギャップを生みやすくなります。
Before:抽象的な仕事内容
「当社のシステム開発プロジェクトに参画し、設計・開発・テストなどを担当していただきます。」
この表現では、具体的にどんなシステムを、どんな言語で、どんな環境で開発するのかが全く伝わりません。応募者は自分の経験やスキルが活かせるのか判断できないのです。
私自身、過去にこのような抽象的な求人に応募したことがあります。面接で詳細を聞いてみると、全く自分のスキルとマッチしておらず、お互いに時間を無駄にしてしまった経験があります。
After:詳細かつ具体的な仕事内容
「金融機関向け決済システムの開発プロジェクトに参画いただきます。Java/Spring Bootを使用したバックエンド開発が中心で、具体的には以下の業務を担当していただきます。
- 要件定義・基本設計のレビュー参加
- 詳細設計書の作成
- コーディングとユニットテスト
- チームメンバーのコードレビュー
開発環境は、AWS上に構築されており、GitHubを使った開発フローで進めています。」
改善後の表現では、開発するシステムの種類、使用言語・フレームワーク、具体的な担当業務、開発環境まで詳細に記載しています。
この改善により、応募者数自体は約20%減少しましたが、書類選考通過率は2倍に向上し、最終的な採用人数は変わらず、採用コストの削減につながりました。

事例3:待遇・福利厚生の見せ方で応募増加
3つ目の事例は、製造業の現場スタッフ募集です。
同じ待遇内容でも、見せ方を工夫するだけで応募者の反応は大きく変わります。特に給与や福利厚生は、応募者が最も注目する部分です。
Before:シンプルすぎる待遇記載
「月給22万円~、各種社会保険完備、交通費支給、昇給年1回」
このような簡素な記載では、応募者に「平均的な会社」という印象しか与えません。何が他社と違うのか、どんな魅力があるのかが伝わりません。
After:詳細かつ魅力的な待遇記載
「月給:22万円~27万円
【給与内訳】
- 基本給:18万円~
- 固定残業代:2万円(20時間分/超過分は別途支給)
- 資格手当:最大2万円(保有資格により支給)
- 皆勤手当:5,000円
【年収例】
- 入社2年目/25歳/年収320万円
- 主任/30歳/年収420万円
【福利厚生】
- 各種社会保険完備
- 交通費全額支給(上限3万円/月)
- 社員寮あり(家賃補助50%)
- 社内表彰制度(四半期ごとに優秀者に賞金3万円)
- 資格取得支援(受験料全額会社負担、合格で祝い金3万円)
」
改善後は、給与の内訳を明確にし、年収例を示すことで将来性をイメージしやすくしています。また、福利厚生も具体的な金額を示すことで、実感を持って理解できるようになっています。
この変更により、応募数が1.8倍に増加し、特に20代の若手応募者が増えました。
事例4:ターゲットを絞った広告配信で採用コスト半減
4つ目は、SNS広告を活用した採用活動の改善事例です。
従来の求人媒体だけでは届かない層にアプローチするため、SNS広告を活用する企業が増えています。しかし、闇雲に広告を出しても効果は限定的です。
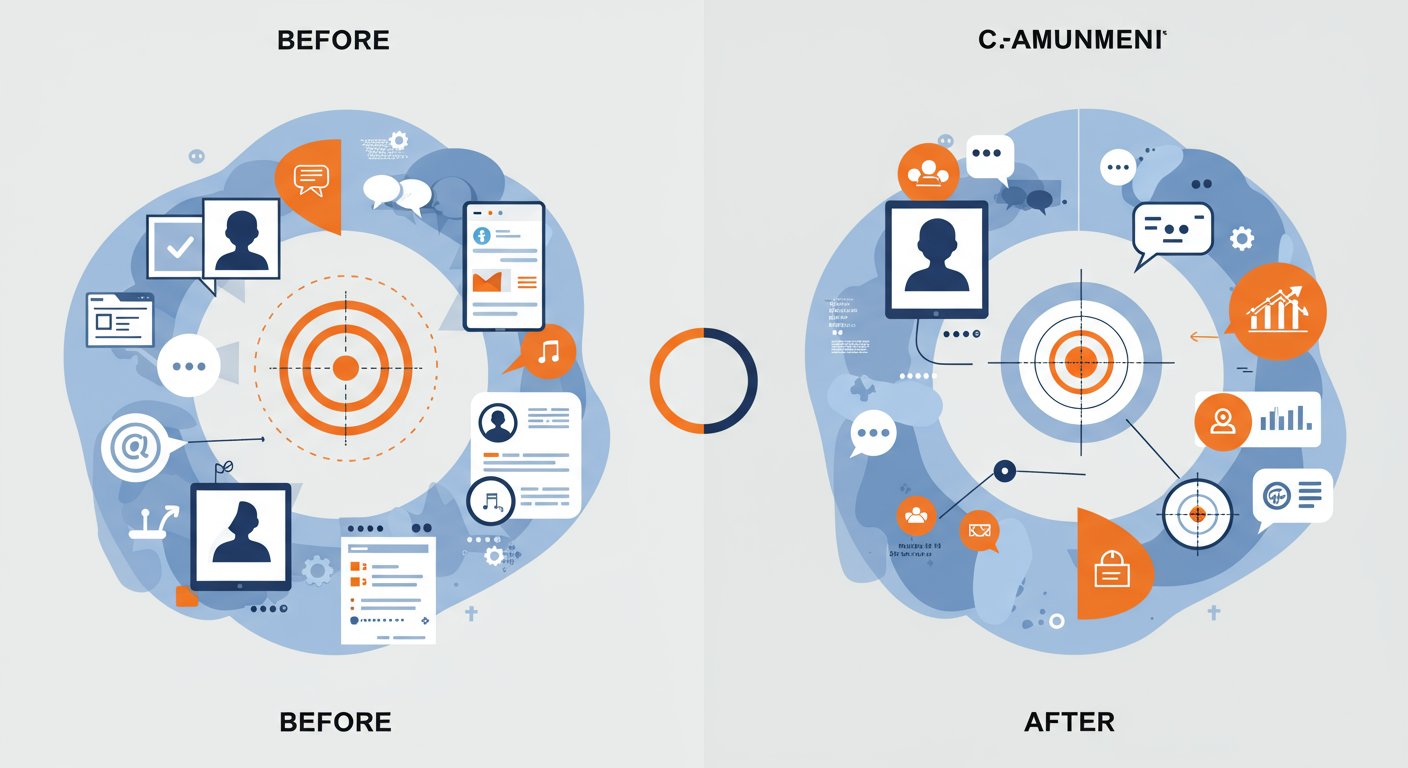
Before:広範囲なターゲティング
ある製造業B社では、若手人材の確保が課題でした。平均年齢が上昇傾向にあり、20代の採用を強化したいと考えていました。
最初は、年齢と地域だけで絞ったFacebook広告を配信していましたが、月間広告費30万円をかけても、応募は月2名程度と効果は限定的でした。
After:精密なターゲティングと創造的なクリエイティブ
そこでB社は、SNS採用広告代行サービスを利用し、ターゲティングを大幅に見直しました。
- 年齢・地域に加え、「ものづくり」「DIY」「工作」などの興味関心でターゲットを絞り込み
- InstagramとTikTokを中心に、実際の工場での作業風景や完成品の動画を使った広告を配信
- 社員インタビュー動画で、未経験から成長できる環境をアピール
この改善により、同じ月間30万円の広告費で、20代の応募者が月2名から10名に増加。さらに、応募者の適性も高く、採用成功率が60%向上しました。
私が担当したある企業でも、同様の改善を行ったところ、採用コストを半分に抑えながら、応募数を3倍に増やすことができました。ターゲティングの精度が採用成功の鍵を握っているのです。
事例5:採用サイトのデザイン改善で応募率アップ
5つ目は、採用サイトのデザイン改善による効果です。
採用サイトは企業の顔。第一印象を決める重要な要素です。特に若い世代は、サイトのデザインや使いやすさで企業の先進性や文化を判断する傾向があります。
Before:情報過多で分かりにくいサイト
あるIT企業の採用サイトは、情報量は豊富でしたが、一つのページに多くの情報が詰め込まれ、何を伝えたいのか分かりにくい状態でした。
テキストが多く、画像や動画が少ないため、閲覧者の滞在時間も短く、応募フォームまでたどり着く人は訪問者の5%程度でした。
After:ユーザー体験を重視したサイト設計
サイトを全面的にリニューアルし、以下の点を改善しました。
- ターゲット別(新卒・中途・職種別)に入口を分け、関連情報にすぐアクセスできるよう設計
- 文字量を減らし、社員の生の声や職場環境を伝える写真・動画を増加
- スマートフォンでの閲覧を最適化(レスポンシブデザイン)
- 各ページに明確なCTA(応募ボタン)を設置
- 応募フォームのステップを減らし、入力項目を最小限に
この改善により、サイト滞在時間が2倍に延び、応募フォームへの到達率が5%から18%に向上。最終的な応募数は2.5倍に増加しました。
あなたの会社の採用サイトは、応募者にとって使いやすいものになっていますか?一度、第三者の目で見直してみることをお勧めします。
事例6:社員の声を活用した採用動画で応募者増加
6つ目は、社員の声を活用した採用動画の事例です。
文字や写真だけでは伝わらない「会社の雰囲気」や「働く人の本音」を伝えるために、動画コンテンツが効果的です。
Before:形式的な企業紹介
あるサービス業C社では、従来型の企業紹介資料を使用していました。会社概要、事業内容、福利厚生などを箇条書きで記載した資料は情報としては正確でしたが、「会社の空気感」が伝わりませんでした。
私も就職活動中、似たような企業紹介を何十社も見ましたが、正直なところ、どの会社も同じように感じてしまいました。企業の個性が伝わってこなかったのです。
After:リアルな社員インタビュー動画
C社は、様々な部署・年代の社員にインタビューした短い動画シリーズを制作。以下のポイントを意識しました。
- 脚本なしの自然な会話で、リアルな雰囲気を伝える
- 仕事のやりがいだけでなく、苦労した点や改善してほしい点も率直に語ってもらう
- オフィスや実際の業務風景を背景に撮影し、働く環境をリアルに見せる
- 1本あたり2〜3分の短い動画を複数制作し、見たい内容だけ選べるようにする
これらの動画をFacebookとInstagramで広告配信したところ、従来の採用広告と比較して問い合わせ数が3倍に増加。さらに、面接での「御社を志望した理由」として「動画を見て雰囲気が良さそうだと思った」という回答が多く寄せられるようになりました。

事例7:応募フォームの簡素化で応募完了率アップ
7つ目は、応募フォームの改善事例です。
求職者が「応募したい」と思っても、応募プロセスが複雑だと途中で離脱してしまいます。特にスマートフォンからの応募が増えている現在、フォームの使いやすさは重要です。
Before:複雑で長い応募フォーム
ある小売業の応募フォームは、個人情報から職歴、志望動機まで含め全部で25項目もの入力が必要でした。応募開始から完了までの平均時間は約18分。フォーム開始者のうち、実際に応募完了まで至ったのは40%程度でした。
長すぎる応募フォームは、「この会社は面倒くさい」という印象を与えかねません。
After:2段階に分けたシンプルフォーム
応募プロセスを2段階に分け、最初のステップでは必要最小限の情報(氏名、連絡先、希望職種)のみを入力してもらうよう変更。詳細情報は、採用担当者から連絡があった後に提出してもらう形式にしました。
この改善により、応募フォームの完了率が40%から78%に向上。応募数は1.9倍に増加しました。
「応募のハードルを下げる」という単純な発想が、大きな効果をもたらした好例です。
事例8:採用広告の掲載媒体見直しで適性の高い応募者獲得
8つ目は、採用広告の掲載媒体の見直し事例です。
「たくさんの応募」より「適性の高い応募」を重視するなら、掲載媒体の選定が重要です。
Before:大手総合求人サイトのみの掲載
あるIT企業では、知名度の高い大手求人サイトにのみ広告を掲載していました。応募数は多かったものの、技術的なミスマッチが多く、書類選考の通過率は15%程度でした。
「数を集めれば良い人材も集まる」という考え方は、必ずしも効率的ではありません。
After:専門性の高い媒体と組み合わせ
大手求人サイトの掲載予算を半分に削減し、代わりにエンジニア専門のコミュニティサイトや技術カンファレンスでのスポンサーシップに投資。さらに、GitHubやQiitaのユーザーをターゲットにしたSNS広告も展開しました。
この戦略変更により、応募総数は30%減少したものの、書類選考通過率は15%から48%に向上。最終的な採用人数は変わらず、採用にかかる工数とコストを大幅に削減できました。
私の経験でも、「どこで」求人を出すかは、「何を」書くかと同じくらい重要です。ターゲットとなる人材が普段利用しているプラットフォームを見極めることが成功の鍵です。
事例9:採用ブランディングの強化で応募者の質向上
9つ目は、採用ブランディングの強化事例です。
優秀な人材ほど、「どんな会社か」を重視します。給与や待遇だけでなく、企業の理念や文化、成長機会などを伝えることが重要です。
Before:求人情報のみの発信
あるベンチャー企業では、採用活動は「欠員が出たら求人広告を出す」というスタイルでした。会社の認知度が低く、応募者は給与や勤務条件だけで判断するため、入社後のミスマッチが多発していました。
After:継続的な採用ブランディング活動
この企業は、採用活動を「求人広告」から「採用ブランディング」へと発想を転換。具体的には以下の施策を実施しました。
- 社員が主役のSNSアカウントを開設し、日常の業務風景や社内イベントを定期的に発信
- 経営者や社員によるブログで、会社の理念や仕事への想いを発信
- 業界カンファレンスでの登壇や技術記事の公開で専門性をアピール
- オフィス見学会や交流会を定期開催し、興味を持った人材との接点を作る
これらの活動を1年間継続した結果、「御社のSNSを見ていました」「ブログを読んでいました」という応募者が増加。書類選考の通過率が向上し、入社後の定着率も20%改善しました。
採用は「点」ではなく「線」で考える。この発想の転換が、採用成功の大きな要因となりました。
事例10:SNS広告の活用で潜在層へのアプローチに成功
最後に紹介するのは、SNS広告を活用した潜在層へのアプローチ事例です。
従来の採用手法では届かなかった「転職を考えていない優秀な人材」にアプローチするため、SNS広告が効果的です。
Before:転職サイトのみの掲載
あるIT企業A社では、エンジニア採用が難航し、3ヶ月間応募者ゼロの状況が続いていました。転職サイトや求人サイトのみに広告を掲載していたため、積極的に転職活動をしている人材にしかリーチできていませんでした。
「良い人材は既に採用されている」という状況に悩んでいたのです。
After:SNS広告で潜在層にアプローチ
A社はSNS採用広告代行サービスを利用し、GitHubやQiitaのユーザーをターゲットにしたLinkedInとTwitter広告を実施。広告内容も「求人」ではなく「技術記事」や「開発環境紹介」など、エンジニアが興味を持つコンテンツを前面に出しました。
この戦略により、応募者数が0名から月12名に増加。特に、「転職を考えていなかったが、広告を見て興味を持った」という優秀なエンジニアの応募が増え、採用コストを50%削減しながら、採用期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮することができました。
SNS広告の強みは、「今すぐ転職したい」と思っていない潜在層にもアプローチできること。これが従来の採用手法との大きな違いです。
採用広告改善の3つの共通ポイント
10の事例を見てきましたが、成功事例に共通するポイントは以下の3つです。
1. 応募者視点での情報設計
採用担当者が「伝えたいこと」ではなく、応募者が「知りたいこと」を優先して情報を構成することが重要です。特に、応募者の不安や疑問を先回りして解消する情報提供が効果的です。
2. ターゲットを明確にした発信
「誰に届けたいのか」を明確にし、そのターゲットに響く言葉や媒体を選ぶことが成功の鍵です。漠然と「優秀な人材」ではなく、具体的な属性や興味関心で絞り込むことで、効率的な採用活動が可能になります。
3. 継続的な改善と効果測定
採用広告は一度作って終わりではなく、応募状況や面接でのフィードバックを基に継続的に改善していくことが重要です。特にSNS広告では、A/Bテストを行いながら効果の高い訴求方法を見つけることができます。
採用広告の改善は、一朝一夕にはいきません。しかし、小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。
自社の採用広告を見直す際は、ぜひこれらのポイントを参考にしてみてください。
まとめ:採用広告改善で理想の人材と出会う
今回ご紹介した10の事例から、採用広告の「見せ方」を工夫するだけで、応募数や応募者の質が大きく変わることがお分かりいただけたと思います。
採用広告の改善ポイントをまとめると以下の通りです。
- キャッチコピーは応募者の不安を解消する内容に
- 仕事内容は具体的かつ詳細に
- 待遇・福利厚生は数字を使って具体的に
- ターゲットを絞った広告配信で効率アップ
- 採用サイトはユーザー体験を重視
- 社員の声を活用した動画コンテンツで差別化
- 応募フォームは簡素化して完了率アップ
- 掲載媒体は量より質を重視
- 継続的な採用ブランディングで認知度向上
- SNS広告で潜在層にアプローチ
採用活動は企業の未来を左右する重要な活動です。「人が集まらない」と諦める前に、まずは採用広告の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。
特に、SNS広告を活用した採用手法は、従来の採用手法では届かなかった優秀な人材にアプローチできる可能性を秘めています。月間30万円から始められる「SNS採用広告代行」サービスを活用すれば、専門知識がなくても効果的なSNS採用が可能です。
貴社の採用課題解決のお手伝いをさせていただければ幸いです。詳しくはSNS採用広告代行のサービス詳細をご覧ください。